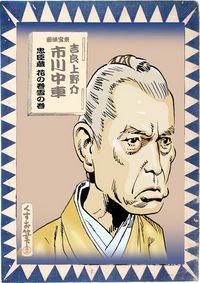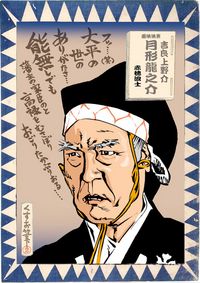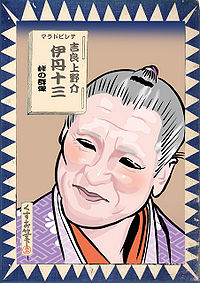吉良上野介
吉良上野介【きら こうずけのすけ】
名門の末裔で、官位が高い「高家」の人。権力志向型。インテリ。仕事は完璧。趣味人。
事件当時、皇室からの使者を江戸城で接待するイベントのリーダーだった。
イベント係の部下、浅野内匠頭からうらまれ、斬りつけられる。吉良のイジメ(パワハラ)が原因とされている。
イジメのきっかけは、自分への浅野の進物がショボかったのにカッと来てからとか(もっともオーソドックス)、自分ところの三河(愛知県)の塩稼業が赤穂より具合悪くて快く思ってなかったとか(「峠の群像」ほか)、吉良が浅野内匠頭の奥さんに横恋慕してふられたとか(仮名手本)というのがドラマでは定石。
レアなところでは、あるお大名のところの掛け物について浅野が吉良をやり込めたのを根に持たれたとか(鍔屋宗伴)、「とにかく虫が好かなかった」(「剣」)。浅野の稚児(ちご)を見染めて「くれ」と言ったが断られた(南條範夫先生談「NHKグラフ」S50.1月号)。etc...
…どっちにしろ、吉良にとって気の利かない&聞き分けの無い、ウマの合わない部下にイラッとした感じ。
ことあるごとに浅野を「田舎大名」とののしり(ちなみに浅野の領地は播磨の国だが、浅野内匠頭個人は東京・築地の生まれ&育ち)、イベント直前に浅野の用意したインテリア(墨絵の屏風)にダメ出しをした上に扇子で真ん中から引き裂いたり、その屏風をぶっ倒したり、用意する料理は精進料理だと嘘情報を流して浅野のケータリングを台無しにしたり。増上寺(見物コース内休憩所)の100枚(とか2〜500枚)からの畳替えのオーダーを内緒にしてたり、書き付けを浅野だけに見せてあげないとか、しまいにゃイベント当日着てくるドレスコードも客を迎える場所も開催時間もことごとく嘘情報を流すなど、徹底的なパワハラをしたら、浅野にキレられて斬られた。傷は浅手。(「峠の群像」のようにイジメもさることながら徹底的な相性の悪さや連絡の悪さが原因とするドラマもある。)
内匠頭の奇行の原因としてもっとも有力なのは、松の廊下で挨拶をした内匠頭を吉良が鼻でフンと笑ったのがきっかけだったという説で、これは後に「ハナでフン忠臣蔵」という芝居になり、現在まで繰り返し上演されている(ウソ)。
昔だし、その地位、コネ、実績、年齢から考えて、目下に対しておごった、傲岸不遜なタチであったんじゃないかと推測する人もいる。(「正史 赤穂義士」渡辺世祐 光和堂/「赤穂義人録」室鳩巣など)
実際に欲深さと横柄さには定評のあった人だそうで(「吉良上野介の正体」佐佐木杜太郎 エルム刊/「上杉と吉良から見た赤穂事件」青木昭博 小林輝彦共著 米沢信用金庫叢書)、親戚関係の津軽公の家来も吉良の態度にブチ切れて殺そうとした過去もあるとか。(「戦国と幕末」池波正太郎 角川文庫)
三田村鳶魚のインタビュー著書には実際に幕末にご馳走役を務めた殿様のスタッフ(家老)の気が変になっちゃったナマ証言が残っているそうで(要出典)、高家の陰湿なコミュニケーションはもう伝統化していた?
事件後、現役リタイア。呉服橋(東京駅付近)から本所一ツ目(松坂町/墨田東両国三丁目)に引っ越し。長っぽそいでっかい家に住んでた。2550坪(約8430m²)。東西の表門〜裏門133m、南北63m(<なに見て書いたのか、計算が合わない。145.8m✕68.2mと、聞いたこともある)。
倒産した赤穂藩の残党が仕返しにくるというウワサからセキュリティ対策はしていたものの、警備員は120(90?150?)名もいながら討ち入りの時はみんな眠ってるところを叩き起こされた上、長屋でスタンバイしてた連中は浪士の数がハンパじゃないと勘違いして出動しなかった。
雪の夜に起き抜けのパジャマ姿、ねぼけまなこ&裸足で応戦した警備は完全武装で47人の浪士に完敗する。
討ち入りされて一家断絶になっちゃったが、吉良さんはなにげに三河では今も名君として評判がいい。
・・・とは言うものの、悪者だって家に帰れば良き夫、良き父にかわることはよくあることで、領地からしぼりとらなくたって吉良ほどの財産と名声があればなおのこと……とは池波正太郎氏の談。(「戦国と幕末」角川文庫/「忠臣蔵と日本の仇討ち」 中央公論社(「歴史と人物(S46.12月号所収)」))
いっぽうで、将軍の代理で京都に出かけるなど、旅費(や衣装代も)など、いちいち莫大なお金もかかり、あっちこっちに相当なツケがたまり、たよりにしたい上杉家も借金があって、その上、火事があったり地元が洪水にあったり、家内の懐事情は相当厳しかったという話もある。(「開館30周年記念特別展 元禄赤穂事件」図録コラムby 谷口眞子 赤穂市立歴史博物館/「上杉と吉良から見た赤穂事件」米沢信用金庫叢書)
また一説には、地元農民が新田開発をがんばった際は免税となり、収入も無い時もあったとか。(要確認)
現代にも一部が残る堤防を作ったことと、農耕用の駄馬にまたがって現場を視察したと伝えられる親近感が、名君の根拠となっている(要確認)が、そのあたりがうまく構成されているのが、稲田和浩先生作の浪曲「赤馬の殿様」である。東家孝太郎師匠の持ちネタ。
Kira Kozuke no suke
In the plays, he is always the villain.
Kira angered Asano, became hated, and was ultimately killed...
I've read in historical records that Kira was described as "arrogant" and that "he drove samurai to madness."
I hesitate to talk about this figure.
Kira’s supporters often defend him, and many feel deep sympathy for his side of the story.
But you know… I believe that what’s portrayed in the plays carries a meaningful message.
南北朝時代事情
南北朝時代を舞台とした人形浄瑠璃や歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」では、吉良上野介は高師直(こうのもろなお)という人物でトレースされている。
高師直は実在した南北朝時代〜室町時代の武将で、室町幕府でのし上がったけっこう悪評の高い贅沢好きの「ばさら大名」。
で、
この時代に南朝vs北朝で闘った天皇たちだったが、南朝軍・楠木正成や新田義貞ら後醍醐天皇軍は、北朝軍の足利尊氏と闘った。吉良上野介はこの足利家の血筋。(ちなみに高師直もだいぶメインで活躍の北朝方)
ゴダイゴ楠木正成は、吉良の先祖・足利尊氏に敗けちゃうんですな。その後も南朝軍はコテンパン。
いろいろあって南北朝は和睦するが、元禄時代になって、藤原氏系(後醍醐天皇のお母さん方の家系)と伝わる大石内蔵助が、足利系吉良家を断絶するきっかけを作り、明治時代になって明治天皇は泉岳寺にことづけ(勅書)で「大石内蔵助たちは義士だ!」とエールを送りお金をくれたりしました。
どうやりゃいいかわからないけど歴史ミステリーをこしらえられそうな面白い因縁です。
ちなみに柄本明は高師直と吉良上野介の両方を演じた珍しい俳優であります。(高師直は南北朝時代を扱ったNHK大河ドラマ「太平記」(91)。吉良は「新春ワイド時代劇 忠臣蔵〜その義その愛」(12))
忠臣蔵ぶろぐ(講演と吉良町観光)
(トークショー備忘録)
(吉良町観光)
(名君説について)
関連項目
関連作品
<吉良が主人公の作品>
- イヌの仇討(こまつ座)〜井上ひさし〜1988
- 梅沢武生劇団の忠臣蔵(梅沢武生劇団)〜大衆演劇〜1990
- 吉良ですが、なにか?(本多劇場)〜三谷幸喜〜2014
- 江戸からきたキラくん(東海テレビ)〜エリアドラマ〜2024
- 身代わり忠臣蔵(東映)2024